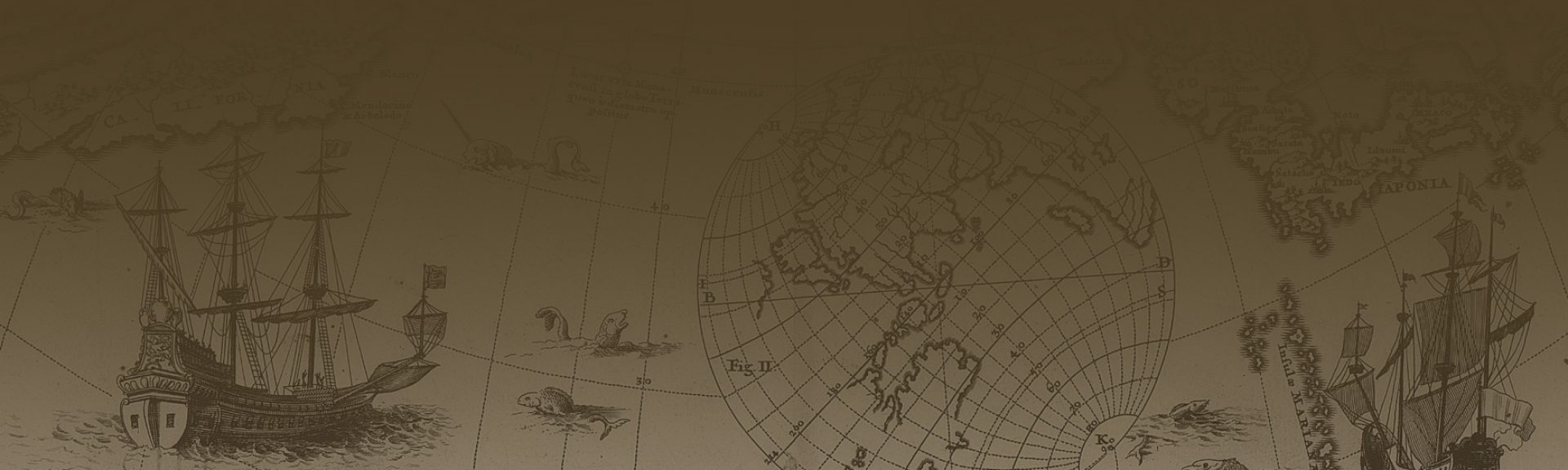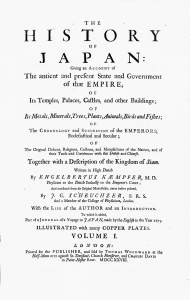ライブラリー図書
日本誌 英語版 全2巻
解説
本書の著者ケンペル(Engelbert Kaempfer, 1651 – 1716)は、ドイツのレムゴー出身の医師、著作家、博物学者です。ドイツ各地及びスウェーデンの大学で研究遍歴を続けながら、博物学、医学、言語学、哲学、歴史学、地理学などの研鑽を積み、30歳になる1681年にスウェーデンへと渡り、1683年からは同国がモスクワ大公国とペルシャに派遣した外交使節団に随行しました。イスファンに2年近く滞在したケンペルは、道中やイスファンで見聞したことを記録し続け、この時の研究成果の多くが本書に盛り込まれています。イスファンからさらに旅を続けることを希望していたケンペルは、オランダ東インド会社の船医となって1689年にバタヴィアへと渡り、翌1690年には日本オランダ商館長付き医師として日本の地を踏みました。同年9月から1692年10月末までの2年余りを日本で過ごす中で2度の江戸参府も経験し、離日後はバタヴィアを経由して1693年にアムステルダムへと戻りました。ケンペルはヨーロッパに戻ってからすぐに著作の執筆と刊行に専念するつもりだったようですが、様々な事情により困難を極め、ようやく生前唯一のまとまった出版物となったラテン語論集『廻国奇観』を1712年に刊行するも、1716年には世を去ってしまいました。残された遺稿や和本、地図類などの膨大なコレクションは、ケンペル没後にイギリスのハンス・スローン(Hans Sloane, 1660 – 1753)に買い取られ、スイスの博物学者ショイヒツァー(Johann Caspar Scheuchzer, 1702-1729)が、スローンの命を受けて編集と英訳を行いました。本書はこうした複雑な背景のもとに、ケンペルの没後10年以上経ってから刊行された作品ですが、その完成度の高さから、18世紀ヨーロッパにおける日本研究の金字塔として絶大な影響力を持つことになりました。
この作品は比較的大きなフォリオ判で全2巻構成となっており、当センター所蔵本は、第1巻冒頭に、「第二補遺」(日英貿易再開を求めるために1673年に来航したリターン号の航海記)が置かれているという、やや変則的な綴じられ方がなされています。以下第1巻は、イギリス国王への献辞、目次、早期購入者リスト、著者序文(i~ivページ〜)、ショイヒツァーによるケンペルの伝記(v~xvページ〜)、ショイヒツァーの序文(xvi〜liiページ)、第1部(1ページ〜)バタヴィアからシャムを経由して日本に到着するまでの旅行記、日本の地理的概観、行政区分、人々の起源、気候や動植物、魚貝類について、第2部(143ページ〜)神話時代から現代(1692年)に至るまでの日本の歴史、第3部(203ページ〜)日本の諸宗教、特に神道、仏教、儒教について、第4部(253ページ〜)長崎の概観ならびに当地における貿易の実情、第1巻収録図版の解説(392ページ)と各種図版、となっています。巻末にまとめられた図版は、日本地図や中村惕斎『訓蒙図彙』から抜粋した生き物たちを描いた図、長崎湾図や小判図などいずれも興味深いものばかりで、これらの図版は、ケンペル自身のスケッチや、彼が持ち帰った日本の書物の挿絵などをもとにしています。
第2巻は、第5部(393〜612ページ)として、ケンペルによる2度の江戸参府旅行記が中心となっており、それに続いて掲載された「第一補遺」(1〜75ページ)では、いわゆる「鎖国論」として後年日本でも知られるようになった論考をはじめとして、『廻国奇観』所収の日本関係論文が英訳された上で6本収録されています。第1巻同様に、第2巻末にも収録図版の解説と各種図版が収録されており、長崎から江戸に至るまでの道中の各種地図や、清水寺や三十三間堂、京都、江戸の市街図、有名な「将軍の前で踊るケンペル」、いろは文字などの図を見ることができます。本書に収録されたこれらの図版は、ケンペル自身や編訳者ショイヒツァーの理解不足のために、誤りや不正確な点もあるものの、現在の私たちが見ても興味深いものばかりで、同時代のヨーロッパでも大きな話題となって、後年に他の多くの書物にも転載されています。
本書が刊行されるまでの西洋における日本研究書としては、カロン『日本大王国志』や、ヴァレニウス『日本国誌』、モンターヌス『オランダ東インド会社遣日使節紀行』などが代表的なものとして知られていましたが、本書は実際に日本で2年も過ごした著者による詳細な日記をもとにした作品であること、著者自身の考察と見解に基づいて日本の歴史や文化などが秩序立てられて叙述されていることから、それまでにない体系的で優れた日本研究書として高く評価されました。刊行されて間もなく、1729年にフランス語訳版、オランダ語訳版が出されていずれも版を重ねたことで、18世紀ヨーロッパにおける日本観の形成に極めて大きな影響力を与えたことがわかっています。モンテスキュー(Charles-Louis de Montesquieu, 1689 – 1755)やヴォルテール(Voltaire / François-Marie Arouet, 1694 – 1778)といった同時代を代表する思想家たちは、日本について言及する際にこぞって本書(とその翻訳版)を典拠とし、また本書の影響を受けて日本を題材にした小説作品が刊行されるなど、本書が多方面に与えた影響の大きさははかりしれません。さらに、本書オランダ語訳版は江戸時代の日本へともたらされ、日本にも大きな影響をもたらしました。
なお、ケンペルの母語であり遺稿の原語であるドイツ語での『日本誌』は、「英訳版」である本書と本来同時に刊行されるはずでしたが、実際には刊行が大幅に遅れることになり長らく刊行されませんでした。フランスのイエズス会士デュ・アルド(Jean Baptiste Du Halde, 1647 – 1743)による、中国についての歴史、地理、文化、政治、自然などを包括的にまとめた著作(Description géographique historique, chronologique, politique et physique de l’Empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise…4 vols, Paris, 1735)が、1747年から1749年にかけてドイツ語訳された際に、その補遺として『日本誌』が第4巻にようやく掲載され、これが事実上の「ドイツ語版」として流通しています。これはフランス語訳版から重訳する形で、テキストの一部や図版の大半を削除した抄訳でしたが、別のドイツ語書物に転載されるなどドイツ語圏では一定の影響を持つことになりました。本書が用いたものとは異なるケンペルの別の遺稿に基づいて、ドーム(Christian Wilhelm von Dohm, 1751 – 1820)が全く新たに編纂したドイツ語版『日本誌』(通称ドーム版)が刊行されたのは、本書刊行から約半世紀も過ぎた1777年から1779年にかけてのことです。
(執筆:羽田孝之)
もっと詳しく見る