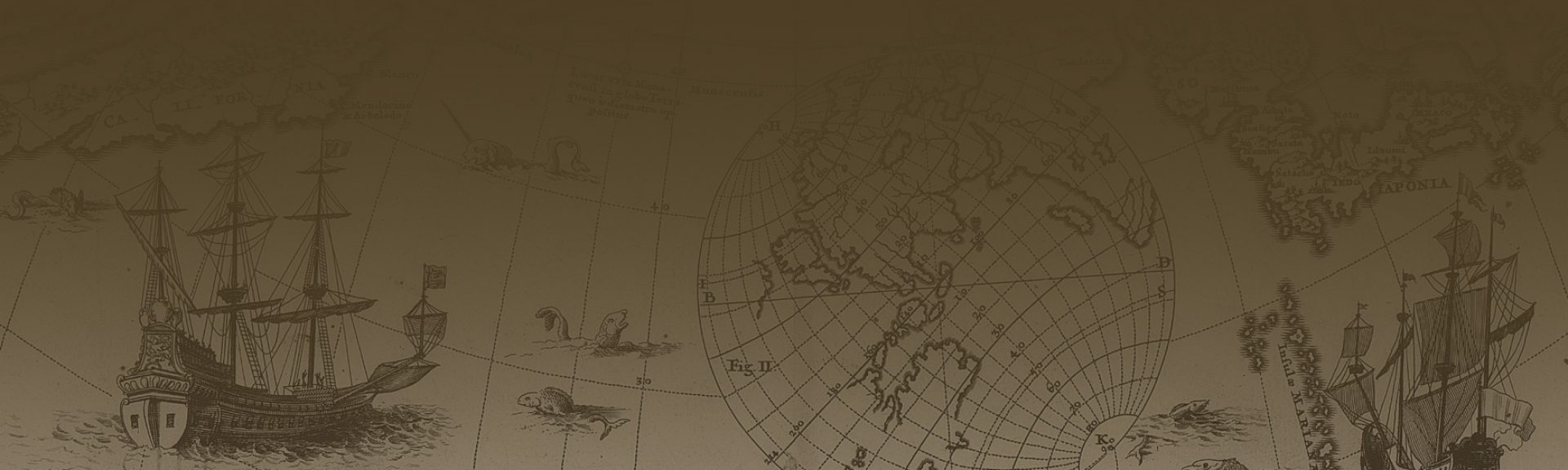学習室先行研究
日本関係欧文図書および平戸オランダ商館に関連する先行研究の一覧を以下5分類に分け、各ページにて掲載しています。
平戸オランダ商館関連(和文)
| 著者 | タイトル・刊行元 | 刊行年 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|
| 森良和 | 「ウィリアム・アダムズの日本人妻 ―その出自と名前をめぐって―」『論叢』玉川大学教育学部紀要2016 | 2017 | 117-134頁 |
| レオナルト,ブリュッセイ | 「東アジアにおけるオランダ東インド会社の盛衰 : 1640-60年代のオランダ商館長日記に関する省察」『東京大学史料編纂所研究紀要』東京大学史料編纂所研究紀要 29号 | 2019 | 36-51頁 |
| リース、ハードリッヒ | 「和蘭國ヘーグ市ニ於る日本歴史ニ関スル古文書」『史学雑誌』第7編第6号 | 1896 | 453ー460頁 |
| 森良和 | 「メルヒオール・ファン・サントフォールト―日本で生きることを選んだリーフデ号船員の生涯」『論叢』(玉川大学教育学部紀要) ― | 2013 | 81ー98頁 |
| 萩原博文 | 「平戸オランダ商館」山田千香子・吉居秀樹編著『平戸・西海学:長崎県北の歴史と文化』桜蘭舎 | 2012 | 203ー227頁 |
| たばこと塩の博物館・江戸遺跡研究会編 | 『シンポジウムVOCと日蘭交流 : VOC遺跡の調査と嗜好品』たばこと塩の博物館・江戸遺跡研究会 | 2010 | |
| 高山和子 | 「『平戸オランダ商館の日記』及び『平戸オランダ商館の会計帳簿』に見られる”kimptouan” と”goude laecken”について」『服飾文化学会誌』Vol. 10. No. 1 | 2009 | 117ー125頁 |
| 小林克、他 | 「桟瓦・レンガのオランダから日本への伝播の実態について―オランダ東インド会社関連遺跡 とその出土資料の分析を通じて―」『住宅総合研究財団研究論文集』No. 34 | 2007 | 337ー348頁 |
| 鈴木康子 | 「日蘭貿易にみる古文書」関場武編『古文書の世界』慶応義塾大学文学部 | 2007 | 87ー110頁 |
| 行武和博 | 「家康政権の対外政策とオランダ船貿易―「平戸商館初期」の日蘭貿易実態 1609―1616年―」『東京大学史料編纂所研究紀要』第17号 | 2007 | 85ー104頁 |
| 行武和博 | 「近世日蘭貿易の数量的取引実態―17世紀前期オランダ商館作成「会計帳簿」の解読・分析―」『社会経済史学』第72号6 | 2007 | 25ー45頁 |
| 行武和博 | 「近世オランダ船貿易の輸入品―分類別品目明細一覧(①17世紀前期)―」『日蘭学会会誌』第31巻1号 | 2006 | 1ー24頁 |
| 萩原博文、前田秀人 | 『海外との交わり・平戸―旧石器時代から現代まで』海外交流史研究会 | 2005 | |
| 堀川幹夫 | 「平戸オランダ商館河内倉庫指図の解読」『桜美林論集』第36号 | 2009 | 102ー120頁 |
| 鈴木康子 | 『近世日蘭貿易史の研究』思文閣出版 | 2004 | |
| 小宮木代良 | 「海賊の謁見」東京大学大学院人文社会系研究科編『8-17世紀の東アジア地域における人・物・情報の交流 : 海域と港市の形成、民族・地域間の相互認識を中心に 下』東大教材出版 | 2004 | 46ー61頁 |
| 萩原博文 | 平戸オランダ商館 : 日蘭・今も続く小さな交流の物語 | 2003 | |
| フィアレイ、シンティア | 「1634年~1661年までの中国と日本の時期の取引に関するVOCの記録」『平戸市史研究』第8号 | 2003 | 19ー32頁 |
| 松井洋子 | 「1622年における日蘭貿易の展望」『東京大学史料編纂所研究紀要』第13号 | 2003 | 1ー26頁 |
| 行武和博 | 「平戸オランダ商館」荒野泰典編『江戸幕府と東アジア』吉川弘文館 | 2003 | 317ー362頁 |
| 木田昌宏 | 「平戸オランダ商館の復元について」『平戸市史研究』第7号 | 2002 | 3ー6頁 |
| 高瀬弘一郎 | 『キリシタン時代の貿易と外交』八木書店 | 2002 | |
| 萩原博文、加藤有重 | 「平戸オランダ商館跡1639年築造倉庫の基礎遺構」『日本考古学』第9巻14号 | 2002 | 145ー156頁 |
| 久家孝史 | 「平戸オランダ商館の江戸参府」『平戸市史研究』第7号 | 2002 | 101ー83頁 |
| 山脇悌二郎 | 『絹と木綿の江戸時代』吉川弘文館 | 2002 | |
| 鈴木達也 | 十七・十八世紀のキセル輸出とオランダ商館―アジアにおけるパイプ喫煙の伝播と拡散― | 2001 | 99ー117頁 |
| 鈴木康子 | 「オランダ東インド会社と日本銀」『花園史学』第22号 | 2001 | 31ー66頁 |
| 永積洋子 | 『朱印船』吉川弘文館 | 2001 | |
| 寺島慶一 | 近世初期の日蘭貿易による鉄輸出の実態『ふぇらむ:日本鉄鋼協会会報』Vol. 5 | 2000 | 29ー36頁 |
| 永積洋子 | 『オランダ商館日記―近世外交の確立』講談社 | 2000 | |
| 平戸市史編さん委員会 | 『平戸市史研究』第5号 | 2000 | |
| 海外交流史研究会 | 『出島以前:平戸海外交流の始まり』長崎労働金庫 | 1999 | |
| 永積洋子 | 「東西交易中易地台湾の盛衰」佐藤次高・岸本美緒編『市場の地域史』山川出版 | 1999 | 326ー366頁 |
| 永積洋子 | 「オランダ史料から見た輸出銀」島根県教育委員会文化財課編『石見銀山遺跡総合調査報告書』第四冊 | 1999 | 122ー130頁 |
| 永積洋子 | 「平戸に伝達された日本人売買・武器輸出禁止令」『日本歴史』611号 | 1999 | 67ー81頁 |
| 平戸市史編さん委員会編 | 『平戸オランダ商館の会計帳簿 : 仕訳帳1640年仕訳帳1641年』平戸市 | 1998 | |
| 八百啓一 | 『近世オランダ貿易と鎖国』吉川弘文館 | 1998 | |
| 梶輝行 | 「徳川幕藩制国家とヨーロッパ軍事技術―17世紀・オランダ商館の軍事的役割を中心に―」箭内健次編『国際社会の形成と近世日本』日本図書センター | 1998 | 153ー192頁 |
| 加藤榮一 | 『幕藩制国家の成立と対外関係』思文閣出版 | 1998 | |
| 萩原博文 | 「平戸オランダ商館の洋風石造倉庫について」野村崇先生還暦記念論集編集委員会編『北方の考古学』野村崇先生還暦記念論集編集委員会 | 1998 | 585ー596頁 |
| 萩原博文 | 「平戸」『考古学ジャーナル』430号 | 1998 | 9ー14頁 |
| 永積洋子 | 「平戸商館はオランダの戦略拠点か」中村質編『鎖国と国際関係』吉川弘文館 | 1997 | 186ー208頁 |
| 行武和博 | 「平戸オランダ商館の石造倉庫に関する史料~1637年および39年建造倉庫の資材・諸経費「明細書」~」『平戸市史研究』第2号 | 1997 | 31ー63頁 |
| 萩原博文 | 「鎖国令によるオランダ貿易の変容」『平戸市史研究』第3号 | 1997 | 112(11)ー88(35)頁 |
| 萩原博文 | 「長崎出島と平戸のオランダ商館」大塚初重、白石太一郎、西谷正、町田章編『考古学による日本歴史10 対外交渉』雄山閣出版 | 1997 | 170ー178頁 |
| 平戸市教育委員会 | 『平戸和蘭商館跡VI・大浜遺跡・浦小川遺跡』平戸市教育委員会 | 1996 | |
| 八百啓介 | 「近世初期のオランダ商館の米輸出と大名財政」『日蘭学会会誌』第21巻第1号 | 1996 | 57ー74頁 |
| 行武和博 | 「平戸オランダ商館の建造物―貿易増加と商館の整備拡充―」『日蘭学会会誌』第21巻第1号 | 1996 | 75ー76頁 |
| 萩原博文、吉福清和、前田秀人、下川達彌、大橋康二、加藤有重 | 「安土桃山・江戸時代の平戸と海外文化」平戸市史編さん委員会編『平戸市史 自然・考古編』平戸市史編さん委員会 | 1995 | 555ー651頁 |
| ミヒェル、ヴォルフガング | 「十七世紀の平戸・出島蘭館の医薬関係者について」『日本医史学雑誌』第41巻第3号 | 1995 | 85ー102頁 |
| 加藤榮一 | 『幕藩制国家の形成と外国貿易』校倉書房 | 1993 | |
| 永積洋子 | 「十七世紀の東アジア貿易」浜下武志・川勝平太編『アジア交易圏と日本工業化1500―1900』リブロポート | 1991 | 103ー128頁 |
| 平戸市教育委員会 | 『平戸和蘭商館跡の発掘III・鄭成功居宅跡の発掘』平戸市教育委員会 | 1992 | |
| 永積洋子 | 『近世初期の外交』創文社 | 1990 | |
| 平戸市文化協会編 | 『紅毛文化と平戸I―江戸初期の国際都市『平戸』―』平戸市文化協会 | 1990 | |
| 萩原博文 | 「平戸オランダ商館築造の遺構について」乙益重隆先生古稀記念論文集刊行会編『九州上代文化論集』乙益重隆先生古稀記念論文集刊行会 | 1990 | 541ー556頁 |
| 前田秀人 | 「オランダ商館をめぐる平戸藩と幕府」『平戸市史研究』創刊号 | 1995 | 108 (1)ー94(15)頁 |
| 行武和博 | 「平戸オランダ商館の対日貿易と商館建造物」『平戸市史研究』創刊号 | 1995 | 9ー55頁 |
| 加藤榮一 | 「『公儀』と「オランダ」」加藤榮一・北島万次・深谷克己編『幕藩制国家と異域・異国』校倉書房 | 1989 | 293ー336頁 |
| 加藤榮一 | 「ブレスケンス号の南部漂着と日本側の対応 附、陸奥国南部領国絵図に描かれたブレスケンス号」『日蘭学会会誌』第14巻第1号 | 1989 | 1ー20頁 |
| 松竹秀雄 | 「タイオワン(台湾)をめぐる17世紀の海外貿易」『東南アジア研究年報』第31集 | 1989 | 25ー68頁 |
| 平戸市教育委員会 | 『史跡平戸和蘭商館跡II』平戸市教育委員会 | 1989 | |
| 科野孝蔵 | 『オランダ東インド会社の歴史』同文舘出版 | 1988 | |
| 長崎県教育委員会 | 『大航海時代の長崎県―南蛮舟来航の地を訪ねて―』長崎県教育委員会 | 1988 | |
| 永積洋子 | 「17世紀の貿易家キコ 別名喜右衛門について」『日蘭学会会誌』第13巻第1号 | 1988 | 1ー20頁 |
| 平戸市教育委員会 | 『平戸和蘭商館跡― 現状変更(家屋改築)に伴なう発掘調査の報告―』平戸市教育委員会 | 1988 | |
| 加藤榮一 | 「連合オランダ東インド会社の戦略拠点としての平戸商館」田中健夫編『日本前近代の国家と対外関係』吉川弘文館 | 1987 | 407ー523頁 |
| 金井圓 | 『日蘭交渉史の研究』思文閣 | 1986 | |
| 加藤榮一 | 平戸オランダ商館の日本人雇傭者について」(尾藤正英先生還暦記念会編『日本近世史論叢 上巻』吉川弘文館 | 1984 | 213ー264頁 |
| 中田易直 | 『近世対外関係史の研究』吉川弘文館 | 1984 | |
| 鈴木康子 | 「近世の樟脳貿易について―オランダ商館の商業帳簿を中心として―」『中央史学』第6号 | 1983 | 35ー60頁 |
| 永積洋子、武田万里子 | 『平戸オランダ商館イギリス商館日記 : 碧眼のみた近世の日本と鎖国への道』そしえて | 1981 | |
| 加藤榮一 | 「連合東インド会社の初期会計記録と平戸商館」『東京大学史料編纂所報』十四 | 1980 | 22ー33頁 |
| 加藤榮一 | 「元和・寛永期における日蘭貿易」(北島正元編『幕藩制国家成立過程の研究』吉川弘文館 | 1978 | 549ー613頁 |
| 永積洋子 | 「オランダ貿易の投銀と借入金」『日本歴史』第351号 | 1977 | 77ー93頁 |
| 中田易直編 | 『近世対外関係史論』有信堂 | 1977 | |
| 太田英蔵 | 「平戸オランダ商館の洋風石造建築について」『風俗』第14巻第2号 | 1975 | 1ー26頁 |
| 加藤榮一 | 「1636年平戸オランダ商館貿易表(2)」『東京大学史料編纂所報』六 | 1975 | |
| 岩生成一 | 『鎖国』中央公論社 | 1974 | |
| 岩生成一 | 「江戸時代の砂糖貿易について」『日本学士院紀要』第31巻第1号 | 1973 | 1ー33頁 |
| 幸田成友 | 『幸田成友著作集 4』中央公論社 | 1972 | |
| 永積洋子 | 「平戸藩とオランダ貿易」『日本歴史』第286号 | 1972 | 1ー19頁 |
| 永積昭 | 『オランダ東インド会社』近藤出版社 | 1971 | |
| 加藤榮一 | 「1636年平戸オランダ商館貿易表(1)」『東京大学史料編纂所報』五 | 1970 | |
| 永積洋子 | 「平戸オランダ商館日記を通して見たパンカド」『日本歴史』第260号 | 1970 | 81ー96頁 |
| 加藤榮一 | 「1636年平戸オランダ商館の輸出入商品」『東京大学史料編纂所報』四 | 1969 | 57ー77頁 |
| 加藤榮一 | 「平戸オランダ商館の商業帳簿に見られる日蘭貿易の一断面」『東京大学史料編纂所報』三 | 1968 | 23ー63頁 |
| 板沢武雄 | 『日本とオランダ』至文堂 | 1966 | |
| 岩生成一 | 「近世日本の海外貿易」『歴史』第25巻 | 1962 | 1ー18頁 |
| 森岡美子 | 「近世初頭における生糸貿易」『歴史教育』10巻9号 | 1962 | 24ー64頁 |
| 岩生成一 | 「日蘭交渉の先駆者ヤン・ヨーステン」『日本歴史』第117号 | 1958 | 16ー29頁 |
| オスカー・ナホッド | 『十七世紀日蘭交渉史』天理大学出版部 | 1956 | |
| 田谷博吉 | 「近世初期日蘭貿易による金銀流出事情」『大阪府立大学紀要(人文・社会科学)』4巻 | 1956 | 169ー181頁 |
| 辻善之助 | 『海外交通史』岩波書店 | 1942 | |
| 小葉田淳 | 「日本の金銀外国貿易に関する研究(一)―鎖国以前に於ける―」『史学雑誌』第44編10号 | 1933 | 1280ー1318頁 |
| 小葉田淳 | 「日本の金銀外国貿易に関する研究(二・完)―鎖国以前に於ける―」『史学雑誌』第44編12号 | 1933 | 1381ー1434頁 |
| 村上直次郎 | 『貿易史上の平戸』日本学術普及会 | 1917 | |
| 村上直次郎 | 『日本と和蘭』日蘭協会 | 1915 | |
| 加藤三吾 | 『平戸しるべ』興風會 | 1912 | |
| 齋藤阿具 | 「蘭人の江戸参府(第一回)」『史学雑誌』第21編第9号 | 1910 | 1027ー1053頁 |
| 長崎市役所 | 『幕府時代の長崎・上』長崎市役所 | 1903 | |
| 村川堅固 | 「セーリスの家康に呈せし請願書に就いて」『史学雑誌』第11編第4号 | 1900 | 507ー516頁 |
| リース、ハードリッヒ | 「オスカー・ナコッド氏の日蘭交通史」『史学雑誌』第9編第1号 | 1898 | 75ー78頁 |
| 本多浅次郎 | 「和蘭の通商及其創立考」『史学雑誌』第5編第7号 | 1894 | 579ー588頁 |
| 本多浅次郎 | 「和蘭の通商及其創立考(承前)」『史学雑誌』第5編第8号 | 1894 | 670ー685頁 |
| 山縣昌蔵 | 「和蘭商館主の書簡(第二十二号の続)」『史学雑誌』第3編第26号 | 1892 | 82-90頁 |
| 山縣昌蔵 | 「和蘭商館主の書簡(承前)」『史学雑誌』第2編第22号 | 1891 | 626-632頁 |
| 「和蘭商館主の書簡(承前)」『史学雑誌』第2編第21号 | 1891 | 542-553頁 | |
| 山縣昌蔵 | 「和蘭商館主の書簡(承前)」『史学雑誌』第2編第20 | 1891 | 468-477頁 |
| 山縣昌蔵 | 「和蘭商館主の書簡」『史学雑誌』第2編第19号 | 1891 | 399-404頁 |
| 山縣昌蔵 | 「徳川時代和蘭通商始末」『史学雑誌』第2編第18号 | 1891 | 335-341頁 |
| 山縣昌蔵 | 「徳川時代和蘭通商始末」『史学雑誌』第2編第17号 | 1891 | 266-270頁 |
| 山縣昌蔵 | 「徳川時代和蘭通商始末」『史学雑誌』第2編第16号 | 1891 | 186-194頁 |
| 山縣昌蔵 | 「徳川時代和蘭通商始末」『史学雑誌』第2編第14号 | 1891 | 56-65頁 |
| 羽田正 | 「東インド会社という海賊とアジアの人々」東洋文庫編『東インド会社とアジアの海賊』勉誠出版 | 2015 | 1-35頁 |
| 中園成生 | 「平戸系突組の盛衰」『島の館だより』Vol. 19 | 2015 | 2-22頁 |
| 安田智子 | 「十七世紀オランダ東インド会社のアーカイブにみられるオリエンタルペーパーについての考察」『和紙文化研究』第24号 | 2016 | 20-51頁 |